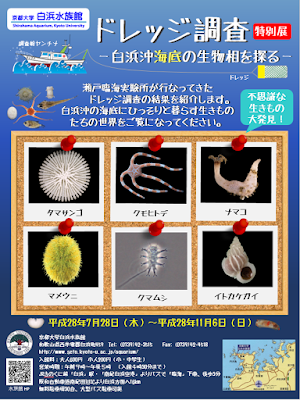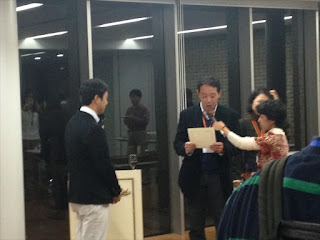我々の研究成果を国立科学博物館の
科学雑誌milsilの「サンゴの知られざる世界」
という特集号に書かせていただきました。
2018年が国際サンゴ礁年ということでもあり、
その年頭の特集として、
分類や進化、生態、そして、
人とのかかわり等という切り口から、
この奥深きサンゴの世界について紹介しています。
我々の記事は15-16ページに掲載されております!
千徳明日香・徳田悠希.海底に潜るイシサンゴ.
milsil「ミルシル」Vol.11 (1), 15-16.(2018)
『milsil』は2008年1月に創刊された
国立科学博物館の科学雑誌で、
広く全国の博物館、会員に配布されており、
一部はミュージアムショップ等で
販売されています(隔月刊・定価400円)。
科学の好きなファミリー層が主なターゲットとなっており、
一般の方でも読みやすい記事になっています。
以下のリンク先で少しだけサンプルが読めます 。